こんにちは。げんです!
今回もあらゆるモノのはじまりを深堀していきましょう。
今回のテーマは、「ことわざ」
皆さんはいくつ「ことわざ」を知っているでしょうか?
たくさん知っている方でも、「ことわざ」自体の起源や意味は説明できるでしょうか?
今回は、そんな「ことわざ」について触れていきたいと思います。

それではさっそく「ことわざ」のはじまりへ!
ことわざとはどういうもの?

まずは「ことわざ」の定義から紹介します。
「ことわざ」とは「昔から世間に広く言い習わされてきたことばで、教訓や風刺などを含んだ短句」という意味です。
古くから伝わる教訓が、短い句として、現在まで語り継がれているということですね。
そもそも「ことわざ」は、「言(こと)+業(わざ)」とされ、「業」には、行為、おこないなどの意味があります。つまり、本来は何らかの実現したい行為に、根拠や意味を持たせるような言葉を表しております。
また、漢字では「諺(言+彦)」と書き、「彦」には、「美しい才徳の優れた」という意味があります。つまり、美しく形式整った言葉などという意味になります。
ことわざのはじまりって何?
はじまりは平安時代
「ことわざ」は、平安時代には既にあったと言われています!

平安時代は「794(なくよ)うぐいす平安京」で始まったから、とんでもなく昔からあるんだな
世俗諺文(せぞくげんもん)ということわざ辞典が出版されており、その中には桃鉄でおなじみ「千載一遇」や、「良薬口に苦し」など、今でも有名なことわざが既に載っているのです。
ちなみに世俗諺文は、全3巻あったのですが、残念ながら上巻しか現存していないようです。
江戸時代には中国古典が到来
江戸時代中期では、中国古典が日本に伝わり、中国の言語を由来としたことわざ多く誕生しました。
そんな中国古典と日本の「ことわざ」が組み合わさり、狂歌(きょうか)と呼ばれる大衆文芸が登場しました。狂歌をよむ人は狂歌師と呼ばれ、現代の放送作家やコピーライターのような存在でした。
狂歌は、現代の「流行語」のような立ち位置で、江戸時代で爆発的な人気を起こしたと言われています。
(おまけ)「故事成語」との違いとは
「ことわざ」について調べると所々「故事成語」という言葉が出てきます。
「ことわざ」との違いは何だろうか。。と思い、調べてみました。
「ことわざ」とは、上記の通り「その国の習わしの教訓」であり、日本だけでなく世界中に存在します。
一方、「故事成語」とは、中国に限った教訓を意味しており、「ことわざ」を中国表記しているだけのようです。
そのため、「故事成語」は、漢字で表現できることが多いです。例えば、「画竜点睛」や、「五十歩百歩」などがあります。
まとめ

今回は「ことわざ」のはじまりについてみてきました。
- 「ことわざ」とは、昔から広く言い習わされてきたことばで、教訓や風刺などを含んだ短句
- 「ことわざ」のはじまりは、平安時代の世俗諺文ということわざ辞典から
- 「故事成語」とは、漢字表記の中国版ことわざのこと
日本のことわざは、平安時代から形そのままに語り継がれており、座右の銘にしている人もいるのではないでしょうか?
先人らの実際に起きた出来事や習わしをもとにしているため、現代でも通用するのでしょう。
皆さんは好きな「ことわざ」はありますか?私は「塵も積もれば山となる」です。
有名なことわざですが、コツコツ小さな努力を続けていれば、いつか大きな成果を得られるという希望溢れる意味があるので、お気に入りの一つです!
というわけで今日も少し賢くなれましたね。
ここまで読んでくださってありがとうございます!それではまた!
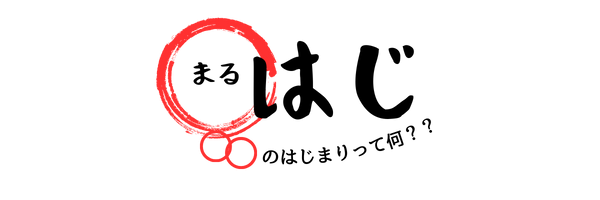
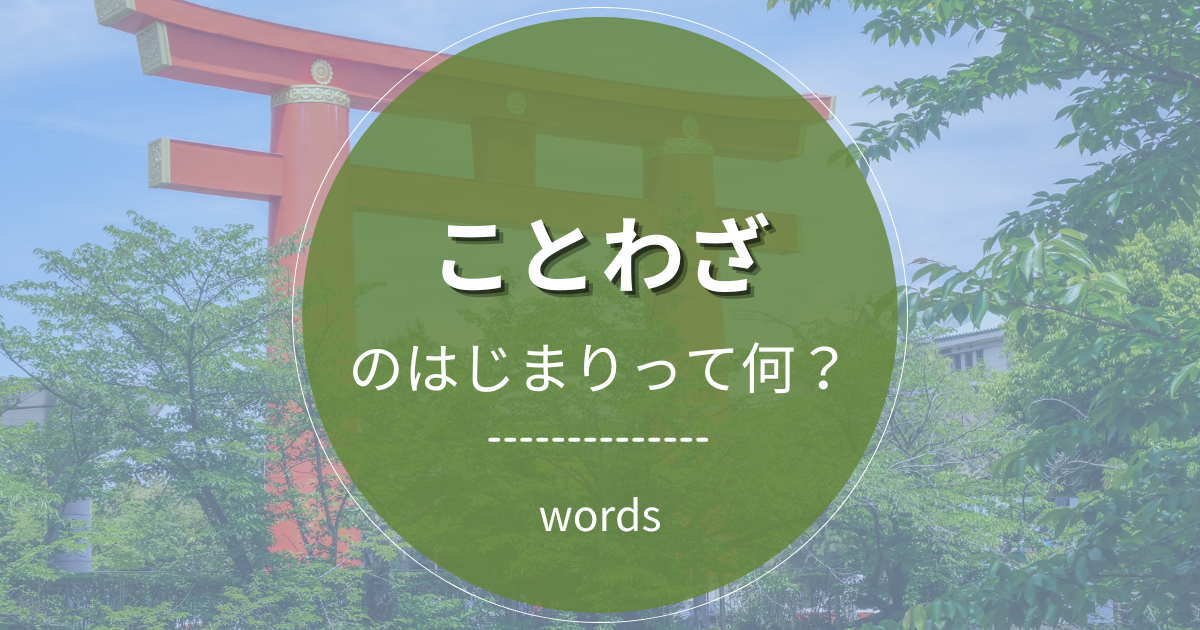


コメント