こんにちは。げんです!
今回もあらゆるモノのはじまりを深堀していきましょう。
今回のテーマは、「アクアパッツァ」
魚を使っているというざっくりした知識はあるけど、具体的にどういう料理なのか。そしてどういう経緯で広まったのか。今回はそんな疑問を解決していきます。

それではさっそく「アクアパッツァ」のはじまりへ!
そもそもアクアパッツァってどういう料理?

「アクアパッツァ」とは、イタリアで生まれた魚介料理です。
白身魚をオリーブオイルで炒め、水や白ワイン、あさり、トマトなどと煮込んで作られます。
主に白身魚の鯛やタラを用いることが多いですが、厳密には食材に決まりはなく、好きな魚介類や、具材を入れることができる、アレンジし放題な料理です。
自由な料理ですが、おしゃれなイタリア料理店で、見かけることが多いことや、魚をまるっと一匹使用している印象から、中々手が届かない料理に思えますね。
実際、私はほとんど口にしたことはなく、一度しっかり食べてみたいんですよね。先に知識だけが溜まってしまいました。。
狂った水?!アクアパッツァの名前の意味
「アクアパッツア」はイタリア語で
acqua:水
pazza:狂った、おかしい
という意味で、直訳すると「狂った水」という意味です。
これは料理の工程に答えがあり、油に水を加える際に、水が狂ったように跳ね回ることが由来です。
…と言いましたが、実際には由来は一つではないのです!
この後の話にも繋がりますが、「船上で作られていたから」や「煮込むだけの美味しさではないから」など、幾つか言い伝えられています。
漁師と農民によるアクアパッツァ誕生秘話
では本題の「アクアパッツァ」のはじまりについて
ずばり…
イタリアのナポリ地方の漁師たちが、船上で獲れたての魚をシンプルに豪快に調理したことがはじまり
まさに「狂った」に名前負けしない起源ですね。当時は塩代わりに海水を使ったり、保存食だったトマトやハーブなどを用いていたと言われています。調理法がシンプルなため、船上で作るにはもってこいの料理だったのです。
漁師料理だったため、はじまりは沿岸地域の家庭料理だったアクアパッツァでしたが、次第にイタリア全土に広がりました。そして、1980年代頃から徐々にイタリア料理が世界を股に駆け出した際、アクアパッツァも一緒に世界へと駆け出していったのです。
調理法が非常にシンプルなことと、見た目のインパクトやアレンジの利きやすさから、瞬く間に世界中の人気料理の一つとなりました。
アクアパッツァと呼ばれたのは農民の知恵から
さて、アクアパッツァの歴史をたどりましたが、実は「アクアパッツァ」の名前そのものは、別に起源があります。
その昔、イタリアのトスカーナ州に住む農民たちは領主にワインを納めていましたが、農民らの手元には、ワインはほぼ残りませんでした。
ワインを欲した農民らは、ワインを作った際の残りものである「ブドウの茎、種、実の搾りかす」などを水で煮込み、発酵させ、独自のワインを作り出しました。
その時作られたワインを「狂った水」、そう「アクアパッツァ」と呼んでいたようです!
そしてナポリの漁師たちが作っていた魚介料理と繋がります。。
その魚介料理のトマトから滲み出る赤い出汁の見た目が、まさに農民らが作ったアクアパッツァの色にそっくりだったんです。
そこから、漁師らが作っていた魚介料理をアクアパッツァと名付けたそう。
元々は農民が残りカスで作ったワインが名前のきっかけだったんですね。
まとめ

今回は「アクアパッツァ」のはじまりについてみてきました。
- アクアパッツァとは、魚をベースに水やトマトで煮込んだイタリア料理!
- アクアパッツァとは、「狂った水」という意味でした
- アクアパッツァという料理は、漁師たちが船上で調理したことがはじまりでした
- アクアパッツァという名前は、農民が領主に納める用に作っていたワインの残り物から作ったワインの名称でした
「狂った水」の名の通り、船上で豪快に作られたことがはじまりのアクアパッツァでしたが、今では世界中で愛される料理へと進化しました。
家ではなかなか作る機会はないと思いますが、是非一度おしゃれ店に足を運んでみてください!歴史を知っていると、また違った気分になるはずです。
私もいち早く食べに行きたいと思います!
ここまで読んでくださってありがとうございます!それではまた!
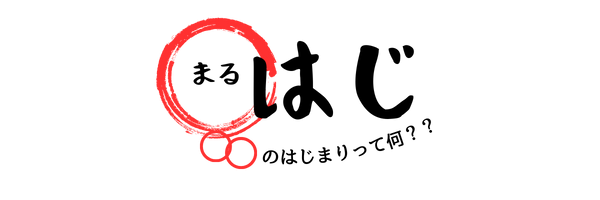


コメント