こんにちは。げんです!
今回もあらゆるモノのはじまりを深堀していきましょう。
今回のテーマは、「ことわざ」
そんな中でも、当記事では「動物」が含まれることわざにフォーカスしていきましょう!
「動物」が含まれるものはたくさんありますが、今回は3つピックアップしていきます!
ちなみに「ことわざ」そのものの起源については、下記の記事で解説してます。

それではさっそく「動物ことわざ」のはじまりへ!
「猿も木から落ちる」のはじまりって何?

まずはことわざの代表格「猿も木から落ちる」から見ていきましょう。
意味
「どれだけその道に優れた人でも、時には失敗することもある」
これは、木登りが上手な猿でも、滑り落ちることはあるという比喩表現になります。
仕事や学校で失敗してしまって、落ち込んでテンションが下がってしまう日もあると思います。そんな時は、このことわざを思い出して、「完璧と思われる人でも失敗はするんだ!」と、うまく立ち直るための活力の一つにしましょう!

類義語に「河童の川流れ」ということわざもあるので、セットで覚えちゃおう!
はじまり・語源
いきなり結論ですが、語源には明確な文献などがありません!
どうやら古くから口伝えで伝わっていったらしいのです。しかし、少なくとも江戸時代には使われていたことは、判明しています。
その理由は、江戸時代に「鷹筑波(たかつくば)」と呼ばれる俳諧撰集に次のような文が残されていたからです。「猿も木から落るたとへの木葉かな」
このことから江戸時代には普通に使われていたのでしょう。
さらにさらに遡ると、紀元前の中国で作られた思想書「淮南子(えなんじ)」には、「猨狖顚蹶して、木枝を失ふ(えんゆうてんけつして、ぼくしをうしなう)」と残されています。
「猨狖(えんゆう)」は「テナガザル」
「顚蹶(てんけつ)」は「つまずくこと」
つまり、「テナガザルも、木の枝を踏み外してつまずく」などという意味になります。「猿も木から落ちる」に非常に近い言い回しですよね。それぐらい大昔から猿は例えに使われていたということです
「虎の威を借る狐」のはじまりって何?
続いては「虎の威を借る狐」について見ていきましょう。
意味
「権力のある者の傍について、威張ること」
「威を借る」とは、「威力を借りる」という意味になります。
現代社会にも、権力者や、腕っぷしが強い人の横には、すねをかじる付き添いが必ずと言っていいほどいます。それは、ドラマやアニメでも当たり前のようにセットで描かれることが多いです。

一番分かりやすい例として、ドラえもんのスネ夫がまさに狐ですね。
ジャイアンという虎の横で、威張り散らかす様子はぴったりです。
はじまり・由来
はじまりは、中国の文書「戦国策(せんごくさく)」に描かれた物語と言われています。
内容を簡単に。。
虎に捕まった狐は、「私は帝から百獣の王になるように命じられたため、私を食べると罰が当たる。嘘だと思うなら付いてきな」と言いました。
虎が後を付いていくと、他の動物たちは虎を恐れて逃げていきます。
そんな様子を虎は自分ではなく、前を歩いている狐のせいだと勘違いしてしまいます
このような話から、「強い者の力を使って威張る」という意味になりました。
ちなみに、この虎と狐の話は例え話であり、中国の「楚(そ)」の国の大臣が恐れられているのは何故か?という疑問の答えに使われた話になります。
「鳶が鷹を生む」のはじまりって何?
最後は「鳶が鷹を生む」です!
意味
「平凡な親が優れた子供を生むこと」
これは、鳶も鷹も同じタカ科の鳥ですが、鷹は飛んでいる鳥を捕まえるほど勇猛なのに対して、鳶はネズミやカエル、小動物の死骸などを食す習性の違いからから出来たと言われています。
同じ猛禽類でも、ここまで真逆の習性をもつのは面白いですね。
ちなみに鳶は、よく海岸線で見かけることが多いと思います。「鳶に注意!!」っていう看板が良くありますよね。食べ歩きをしていたら、上空から食べ物をかっさらっていく姿、見たことあるのではないでしょうか。

友人も鳶の被害にあったことあります。
こんな不名誉なことわざに使われる鳶のくせに生意気ですね。
はじまり・由来
では、なぜ数いる鳥の中から、「鳶」と「鷹」が選ばれているのか、それは古くからの風習である「鷹狩」が関係しているのではと考えられています。
字のごとく、鷹を操って獲物を狩ることなのですが、それは貴族の遊びの一つとしてとても人気でした。鳶は、性格や体格、習性などから、鷹狩は合わなかったとされています。
このことから、「鳶」と「鷹」を比較対象の例として使われることになったのです。
話は逸れますが、対義語には「蛙の子は蛙」というのもあります。
私たち人間も、親と子は基本似るものですが、たまに「なんで君からあんなに優秀な子が生まれてきたのか不思議」みたいな家庭もありますよね。
それは、親は鳶と思っていたけど実は鷹だったのか、生まれた時は鳶だったが努力して鷹に成長したのか。「能ある鷹は爪を隠す」ということわざにも繋がりますね。
こんな風に、ことわざって有名なものでも連鎖的に意味や背景が繋がっていく面白さがあるので、是非皆さんもいろんなことわざを勉強してみてはどうでしょう?
まとめ

今回は「動物」が含まれることわざのはじまりについてみてきました。
- 「猿も木から落ちる」とは、どんなに優れた人でも失敗することもあるという意味
- 「虎の威を借る狐」とは、権力のある者の傍で威張るという意味
- 「鳶が鷹を生む」とは、平凡な親が優れた子供を生むという意味
昔から共存してきた動物にまつわることわざは山ほどあります。今回はほんの一部ですが、使える場面が多い3つだと思います。どうせ使うなら意味と背景を正しく理解してかっこよく使ってみましょう!
個人的には、「虎の威を借る狐」が一番お気に入りで、使いやすいと思います!リアルでこういう人結構いませんか??
では!ここまで読んでくださってありがとうございます!また別の記事でお待ちしています!
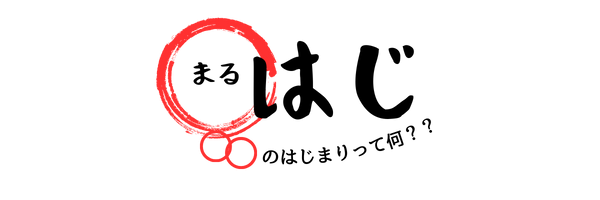
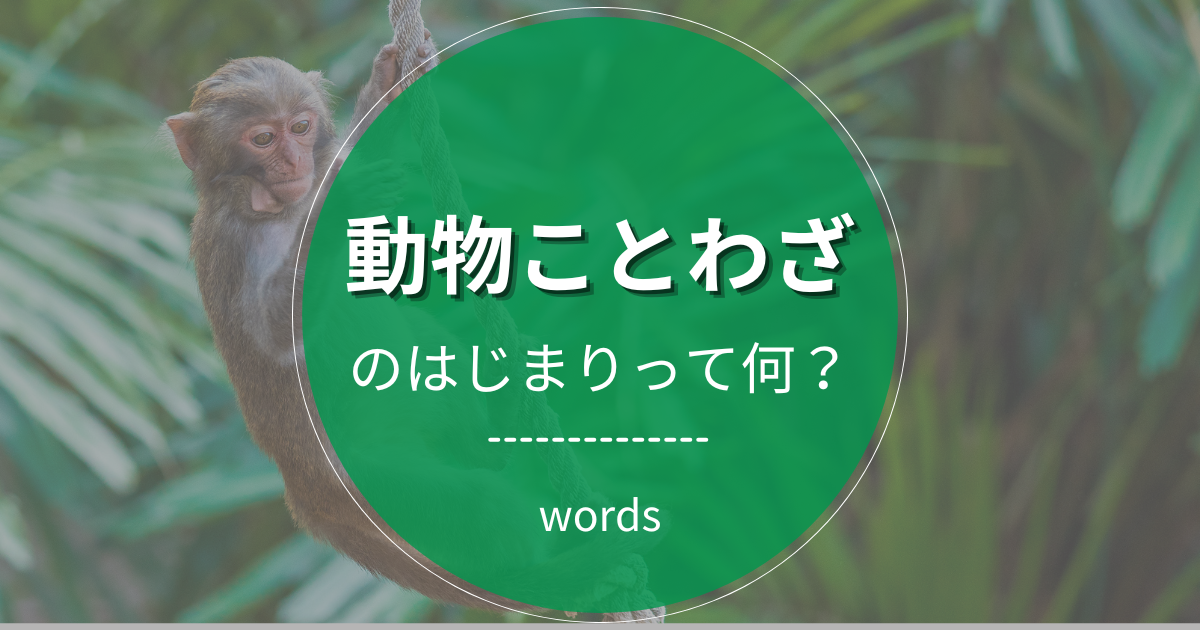



コメント