こんにちは。げんです!
今回もあらゆるモノのはじまりを深堀していきましょう。
今回のテーマは、「バスケットボール」
知らない人はいないであろう学生がしていたらモテるスポーツの代表格!バスケットボール!いまだにバスケをしている人が一番かっこよく見えます。
そんなバスケットボールはいつ、どこで誕生したのか。そして日本に伝わったのはいつ頃なのか、当記事で解説していきます!

それではさっそく「バスケットボール」のはじまりへ!
バスケットボールのはじまりって何?

「バスケットボール」は、野球やサッカーのように、大昔から原型があったスポーツではありませんでした。
実は一人の人物がゼロから作り出したのがスポーツなのです!
アメリカ教授が生み出したスポーツ
1890年頃、アメリカのマサチューセッツ州スプリングフィールドの国際YMCAトレーニングスクールのジェームズ・ネイスミス教授により考案されました。
当時、アメリカでは、アメフトやフットボールなどが主流のスポーツでした。しかし、いずれも屋外スポーツで、冬の雪が積もるシーズンでは、屋内でマット運動や跳び箱しかできませんでした。
そんな中、ネイスミス氏は冬でも屋内で出来るスポーツを考えてくれと言われたのです。そこで目を付けたのが、桃を入れる籠とサッカーボールでした。
その籠を体育館の高い位置に取り付け、2チームでボールを籠に投げ入れて競う球技を考えました。
籠は英語で「basket(バスケット)」になりますので、そこから「バスケットボール」と名付けられたそうです。
はじめは13のルールが作られ、全米でプレイされるようになりました。
~ 13のルール ~
- ボールは片手、両手でどの方向にも投げられる
- ボールは片手、両手でどの方向にも叩けるが、拳で叩いてはいけない
- プレイヤーはボールを持ったまま走ってはいけない
その場で投げるか、他プレイヤーに渡さなければならない - ボールは手で持たなければならず、腕や体を使ってはいけない
- 肩を使って他プレイヤーを押す、押さえる、引っ張る、またはつまずかせてはいけない
最初の違反にはファウルが宣告され、二度目は退場となる - ボールを持っているプレイヤーに対して腕や体を使って押し戻してはいけない
- ボールがゴールに投げられたとき、ゴールと判断されるのはバスケットに入ったときのみ
ただし、防御側がバスケットを動かした場合は、得点としてカウントされる。 - ボールがコートの境界線を越えた場合、最初に触ったプレイヤーがボールを再投入する権利を持つ
5秒以内に再投入しなければならない - プレイヤーがボールを再投入する際、相手チームは妨害してはいけない
- 審判は、プレイヤーがファウルを犯した場合やルールを破った場合に違反を宣告する権限を持つ
- 審判は、ゲームの進行、時間、得点を管理し、ゲームの公式な裁定を行う権限を持つ
- ゲームは、15分のハーフに分かれ、その間に5分の休憩がある
- 一番多くのゴールを決めたチームが勝者
1891年には、国際YMCAトレーニングスクールで18人の学生で初試合も行われました。学生たちはクリスマス休暇などで各自の故郷で「バスケ」を持ち帰り、少しずつ全米に浸透されていきました。
そして日本へ。。
日本に「バスケ」が伝わったのは1908年になります。
YMCAの卒業生だった大森兵蔵さんが東京YMCAで紹介したことがきっかけです。
それ以降、瞬く間に全国的に流行し、あらゆる学校で取り入れられました。
1930年には、日本バスケットボール協会(JABBA)も設立され、2005年に日本プロリーグが発足しました。ちなみに「JABBA」は、今は「JBA」に改称されています。

日本で広まり、プロリーグができたのは想像よりも最近だな
バスケットボール用具やルールの遷移は?
これまで「バスケットボール」の歴史について紹介してきました。
ここからは、ネイスミス氏が考案した当時の姿から、現代バスケへどういう遷移をしていったか見ていきましょう。
バスケの命「ゴールリング」は桃の籠から
先でも述べたように、最初のゴール籠は、桃の籠からでした。
しかしそれだと、ボールを入れる度に、籠から取り出さなければいけません。そのため当時は専属の「ボール取り出し係」がいました。ボールが入ると、はしごや脚立、棒を使ってボールを取り出すのです。
さらに、耐久性も問題視されておりましたが、そこで考えられたのが、金属製の円筒形のものでした。
そこから、1912年頃にボールが勝手に落ちてくるように、お馴染みの金属リングにネットがぶら下がった形になったようです。
ちなみに、ゴールの高さは皆さんは何メートルかご存じでしょうか?
ゴールの高さは10フィート(305cm)であり、これは桃の籠時代から現代まで変わってないのです!
また、ゴールの内径45cmというのも変わっていないのです!
高さなんて、都度調整されてそうなものなのに、一度も変わったことがないなんて驚きですね。
バックボードは存在していなかった
今ではゴールとセットになっているバックボード。ゴールの後ろにある四角い板のことです。
学生のころ、よくあの板の四角い枠を狙って打てと言われたことがありますが、「バスケットボール」ができた当初はそんな板はありませんでした!
「バスケットボール」の人気が上がり、観客も増えてきた頃、観客がゴールに入るのを邪魔するようなことが多発しました。それでは試合にならないと考え、妨害防止に作られたのがバックボードです。
当初は木の板や金網などを用いられていましたが、今度は観客からそれだとゴールに入ったかが見えにくいというクレームが入りました。
クレームが多くて大変ですね。。
そこで今では主流のプラスチック製の板が使われるようになりました。
バックボードができたことで、初心者にもゴールに入れやすくなったり、レイアップなどの技術も生まれ、さらに発展していきました。
ドリブルは最初は禁止でした
3. プレイヤーはボールを持ったまま走ってはいけない
上記で書いた13のルールの一つにある通り、当初はドリブルが禁止だったのです。
当時、人気だったアメフトのような怪我が多いスポーツにしたくないというネイスミス氏の願いから、フェアプレイがないように、ぶつからないように、と考えられたルールです。
しかしその中で「自分へパス」をすることで、敵をかわすテクニカルなプレイヤーが現れ、そこから現代のドリブルに繋がったといわれています。
公式で最初にドリブルの技術が記録されたのは、1897年とのことです。
まとめ

今回は「バスケットボール」のはじまりについてみてきました。
- バスケットボールは、アメリカ人教授が一人で考案したスポーツでした
- ゴールは、最初桃の籠であり、籠の球技から「バスケットボール」と命名されました
- 最初はバックボードもドリブルも存在していませんでした
いかがでしたでしょうか?
野球やサッカーと違い、割と新しいスポーツだということが判明しましたね。それでも今や世界で競技人口トップに入るほどの大人気スポーツに成り上るんですから、ネイスミス氏の功績は素晴らしすぎます。
私はバスケができないのでモテませんが、皆さんはプレイと知識の両刀で持てること間違いなしです!
ここまで読んでくださってありがとうございます!それではまた会いましょう!
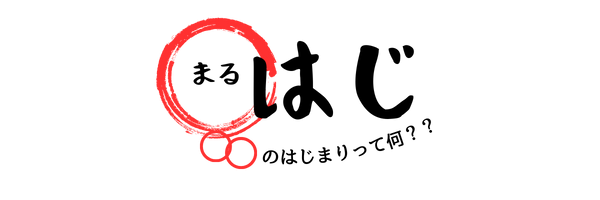



コメント