こんにちは。げんです!
今回もあらゆるモノのはじまりを深堀していきましょう。
今回のテーマは、「サッカー」
200以上の国で愛されている世界的人気のスポーツの「サッカー」ですが、皆さんはその語源や起源についてご存じでしょうか?
好きな人は多いと思いますが、語源まで考えたことないよっていう人がほとんどだと思います!私もその一人です!
今回はそんな「サッカー」の歴史を紐解いていきたいと思います。

それではさっそく「サッカー」のはじまりへ!
サッカーのはじまりって何?

そもそも「サッカー」は、ボール一つあれば誰でもできるスポーツです。それほど簡単にできる「サッカー」なので定義も曖昧であり、明確な起源は判明していません。
ただその中でも特に有力な説が4つあります。
今回はその4つの「中国説」「イタリア説」「中世イングランド説」「キリスト教祭説」を紹介していきます!
①中国説:FIFAが認めた最有力説!
まずは、最も有力な説である中国説から紹介します。
紀元前から続く中国の伝統文化に「蹴鞠(スーキー)」と呼ばれる球技がありました。
初めて史実に登場したのは紀元前2697年にもなります!
紀元前300年以上前の「斉(せい)」では、軍事訓練の一環とし取り入れられました。ルールは、1チーム12人で、鞠を蹴りあい、球門と呼ばれるゴールに蹴り入れた数を競いあうというものでした。
既に現代の「サッカー」と近しいものを感じますね。
当時は、貴族の遊びとしても親しまれており、楽しすぎて仕事をさぼる人が続出したのだとか。そのため、禁止令も出されるほどの人気だったようです。
時代が進むにつれ、チーム競技というより、一人でボールを落とさないようにするリフティングのような姿へと変わっていきました。それが日本にも600年代に「蹴鞠(けまり)」として伝わっています。
「けまり」なら聞いたことある人もいるのでは。
ちなみに最も有力説と伝えたのは根拠があり、あのFIFA(国際サッカー連盟)が、中国説を発祥として述べているからです。
②イタリア説:ルールは最も近い?
次に紹介するのはイタリア説です。
8世紀のイタリアの宮廷で行われていた「カルチョ」という球技が起源というものです。
「カルチョ」とは、イタリア語で「蹴る」という意味です。
これまた貴族の遊びだったため、一般の庶民は見ることしか出来なかったようです。
また「カルチョ」には、一定のスペースの中で実施するや、プレイ人数などルールも細かく設定されており、現代サッカーに近い形だったといいます。
③中世イングランド説:敵の首を蹴る残虐起源
続いては、これまた有力な説中世イングランド説です。
8世紀頃のイングランドでは、戦争に勝利すると敵将の首を切り落とすという残酷な風習がありました。そして戦争に勝利した兵士たちは、その首を蹴って遊ぶという考えられないことをしており、そこからボールに代わってサッカーに繋がったというのが、この説です。
ルールは、地域によって手の使用有無など様々な違いがあったようです。
④キリスト教祭説:何でもありの大祭り!
最後は、中世イングランド説と繋がるところもあるキリスト教祭説です。
イングランドのダービージャー州の街、アッシュボーンでは毎年「シュローブタイド・フットボール」というお祭りが開催されていました。
その祭りが起源だという説になります。
大まかな内容は、7000人程の人が出身地などで2チームになり、1つのボールを奪い合って先に目的地に運んだものが勝ちとなります。
「殺してはいけない」「教会、墓地には入らない」以外のルールは特に決められてなかったため、暴力や乱闘は当たり前で、死人やけが人は続出。そのため、幾度となく禁止令が出されてきたのです。
現代サッカーへどうやって発展した?
「サッカー」の起源を紹介しましたが、現代サッカーとして広まった経緯をここからはみていきましょう。
フットボールの繁栄
現代サッカーのはじまりは、イングランド北部のシェフィールドのパブリックスクールでプレーされるようになったことです。
当時は、手で持っても良いというルールもあり、非常に曖昧なルール設定でした。
そんな曖昧さを統一させようという動きがあり、おおよそのルールは決定できたのですが、肝心の手の使用有無については、手を使わない派代表の「ケンブリッジ大学」と、手を使っていい派代表の「ラグビー校」に勢力が二極化していました。
最終的には、1863年にロンドンで会議が行われ、手を使わないルールが選ばれました。
その後、教会式フットボール(Football Association)、略して「FA」が創設されました。
ちなみに、察しの良い方はお気づきかもしれませんが、最終的に負けてしまった手を使っていい派の「ラグビー校」は、8年後に手を使って行うフットボールとして「ラグビー」を作り上げていったのです。
そして、イギリスで起きた「産業革命」によって、イギリス人が船に乗って全世界に渡り、「サッカー」も一緒に広まっていきました。ボールさえあれば成り立つため、瞬く間に世界中で人気のスポーツとなりました。
日本にも到達!
1873年に、日本にも「サッカー」は伝わりました、
イギリス海軍のダグラス少佐が、日本海軍に訓練の余暇として教えたのがきっかけです。
1918年には、日本フットボール大会も開催され、それは現在の高校サッカー選手権の前身となります。ただし、日本では同時期に野球も伝えられており、野球の方が先に人気沸騰したようです。
野球の起源についてはこちらの記事で解説しています。
最後にサッカーの語源って何?
サッカーの歴史を紹介しましたが、なぜサッカーと呼ばれるのかについて、最後に解説して締めくくろうと思います。
語源はずばり、「FA」からです!
Football Associationの、Associationから、「soc」を拝借し、そこに、「〇〇する人」という意の「~er」をつけて、「soccer」となったのです。
「~er」は、よく見かける表現で日本独自でもマヨラーなぞと言う造語がありますね。
まとめ

今回は「サッカー」のはじまりについてみてきました。
- サッカーには4つの有力な起源説があり、中国の説がFIFAも認める最も有力な説!
- 現代サッカーは、イングランドで誕生し産業革命によって世界中に流行していきました
- 「サッカー」は、「Association」の「soc」と、「〇〇する人」という意の「~er」の組み合わせでした
何かを蹴っていればそれはサッカーの起源だって言われることもあって、たくさん説がありましたね。その中でも中国が最も有力だというのは驚きでした。
ただ、小さいころに見た”少林サッカー”って映画のインパクトがいまだに脳裏に焼き付いています。中国とサッカーの繋がりは、私たちが思っているよりも太いのかもしれませんね。
というわけで今回はスポーツ知識が一つ増えましたね。
ここまで読んでくださってありがとうございます!それではまた!
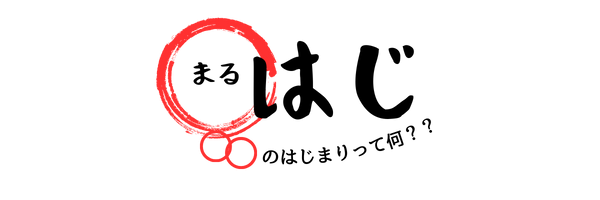
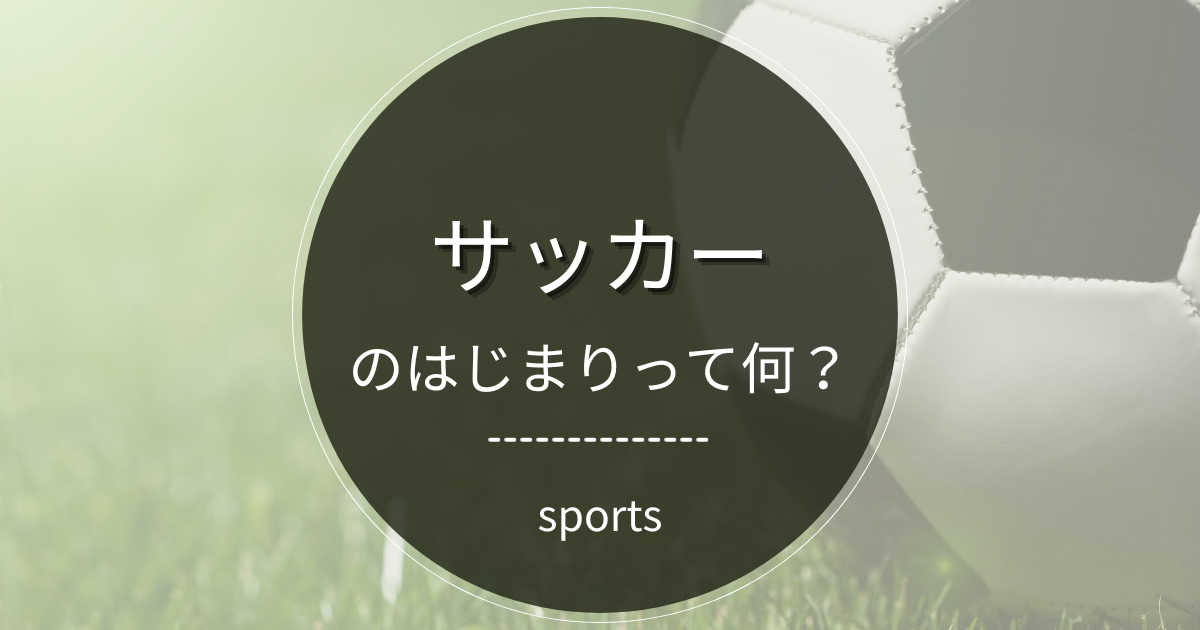



コメント